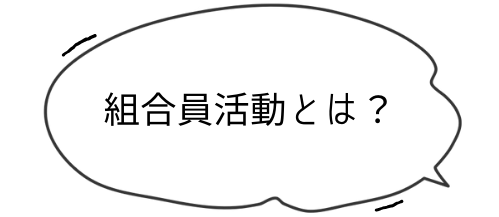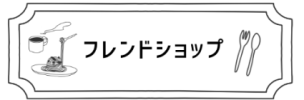組合員活動報告
【2024年度理事研修報告vol.6】理事研修3日目(1) 「ガマ見学」後編
2024年度の理事研修として“平和”をテーマに2025年1月12〜14日に沖縄を訪れました。
各報告を掲載して行きます。
「シムクガマ」の方は米兵がガマにやって来た時、バスの運転手としてアメリカで働いた経験もあるハワイからの帰国者、比嘉平治氏(当時72歳)と比嘉平三氏(当時63歳)の2人が、米兵と英語で交渉。「アメリカ人は人を殺さないよ」と、騒ぐ避難者たちをなだめ説得して、ついに投降へと導きました。ガマ避難民の中に日本兵がいたら自らが米兵に銃殺されるかもしれないリスクを犯しつつ、更に日本人からも「英語が話せる」「米国からの帰国者」というだけで「非国民」と呼ばれたであろう時代に、1000分の2人が冷静に対応できたことで助かりました。たった0.2%です。ガイドさんは「ごく少数の意見でも勇気を持った2人のおかげで住民は助かったのです。
戦時中は異端扱いされていただろうけど、正しいと思うことは勇気を持って言う事も大事」だと話されていました。比嘉氏が村の実力者だったから他の村民に話を聞いてもらえた。という可能性はあるみたいですが、アメリカという国を知っているリーダー格の存在が生死を分けたようでした。この事実に基づいて波平区では、命を救った二人の先輩に感謝の意をこめて洞窟内に記念碑を建立してありました。当時は「非国民」でも今は「英雄」なので、時代とは恐ろしいものです。

この2つのガマの話でキーになるのが、日本軍・政府の情報操作=(皇民化)教育です。天皇陛下のために命を散らせと言われていた時代、進むも地獄・戻るも地獄なら、自分はどちらを選択するだろうか・・・やはり正しい情報がなければ、正しい判断はできないと想像します。しかし正しい情報があったとしても、大多数の意見が国の方針に従ってしまうような時に、比嘉氏のように相反する姿勢を示すことは、やはり大変勇気のいることだと思いました。コロナの時にも感じましたが、表現の自由が認められている現代でも同調圧力に屈している日本人は多いので、大多数の意見に異を唱える勇気を持って述べられるように、己の在り方も見つめ直す必要を感じました。
「チビチリガマ」の前に男性の像が建てられていましたが、伝達役として「シクムガマ」と「チビチリガマ」を行き来していた少年だった方とのことでした。少年は家族を「チビチリガマ」に残し「シクムガマ」に伝達しに行き、そのまま米軍の捕虜になり生き残ることができました。しかし少年が待てども暮せども「チビチリガマ」の家族と再会することはできなかったのです。悲しい事実を知った少年は一時は自暴自棄になり荒んだ人生を送りますが、晩年「チビチリガマ」の悲劇に向き合い語り部となり後世に平和を伝えることに尽力されました。その功績により「世代を結ぶ平和の像」として「チビチリガマ」の前に像が建てられ、今も家族と村民の死を弔っているそうです。
今回の研修では戦後80年経ってもまだ終わらない「オキナワ」を通じて、平和は自分たちの努力の積み重ねが作っていくものだと、改めて感じました。過去の歴史に学び、平和な未来をつくっていくために私たちはどう行動していくべきなのか、組合員の皆さんとも意見交換し考えていきたいと思いました。(藪崎)