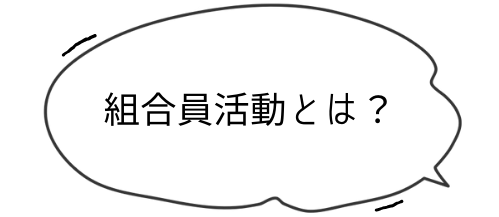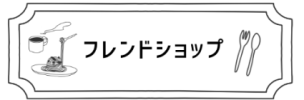組合員活動報告
【報告】4/26 PFASって何?!検査で何がわかるの?〜くらしの安全を守るには〜
■理事会
農薬の残留検査をはじめ放射能検査など、年間500件にものぼる商品検査をお願いしている、農民連食品分析センター所長の八田さんによる学習会を開催しました。
1995年、日本のWTO協定加盟による農産物輸入増加で、検査の簡略化-国内税関での再検査禁止などに加え、基準の緩和など、輸入食品の安全性が不安視されていました。輸入食品や農産物について、科学的且つ中立な立場での検査施設の必要性から、農民連食品分析センターは農業者と消費者の募金により設立されました。
企業や行政などの影響を受けない、独立した立場で活動する世界的に見ても珍しい施設です。募金で生まれ支えられた施設が、これまで日本の食品衛生の分野でどういった役割を担ってきたのか、そして最近、その汚染が報道されるようになったPFAS(ピーファス)について伺いました。


PFASとは単体の物質名ではなく、一万種類以上ある有機フッ素化合物の総称です。人への毒性が指摘され、永遠の化学物質と呼ばれています。防水スプレー、フライパン、家具、化粧品、スマートフォン、生活においてありとあらゆる製品にそれらは潜んでいます。
浄水器の使用期間とPFAS減少率の関係や、下水汚泥肥料からの検出値についてなど、くらしのまわりの調査データを交えてお話しいただきました。検査しなかったらなかった事になる国ニッポン。科学的で中立な検査データの重要性は、今後ますます増していくのではないでしょうか。有機フッ素化合物は、水俣病の原因物質である有機水銀ほどの強度の毒性があるわけではないということですが、避けるに越したことはありません。冷静に対応していきたいと感じました。
まずは知ること、そして、選ぶことの大切さを改めて痛感しました 。
<参加者の声> ※一部抜粋
- 歯のふっそとか、こむぎとか給食のごはんとか、へんなものがなくなればいいと思いました(小学生)
- 大変深く難しい問題ですが・・・・軽やかにわかりやすくお話しいただきありがとうございました。どこかの国、誰かのことではなく、私たち一人ひとりのことだと実感ができました。このような命にかかわるたいせつなことは、学校教育現場の授業の一環として取り入れて欲しいと願います。他人事でなく、日々の日常生活から何をどのように選択するか、意識を持って行動したいです。
- 会場は満席でPFASに関する意識が高いことが感じられました。分析センター八田さんのお話しは駆け足ながら、興味深いデータを基に、とてもわかりやすかったです。PFASが今後どの様に影響するかわかりませんが食は命です。目に見えないものだからこそ、地道な分析を続けていただきたいです。
- 募金で生まれた施設が国民の命と健康を守る活動をしてこられたことを恥ずかしながら知らなかったです。不安を感じたものは、検査して、健康被害があるかどうかを医学的にはっきりさせる両輪で進めて行って欲しいと思います。そのような情報を開示して、国民がそのようなものを使わない意識を持って暮らす社会になるようにと強く望みます。ユーモアを混じえたあきないお話しで、ありがたく聞かせていただきました。